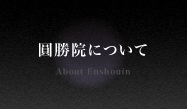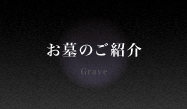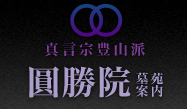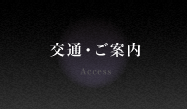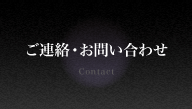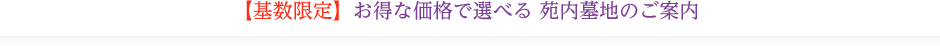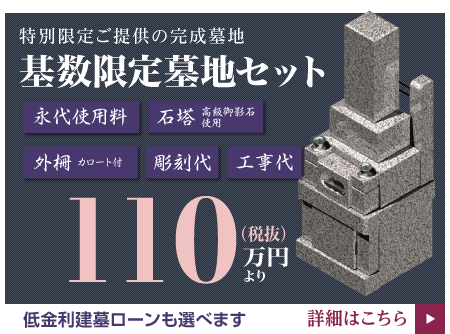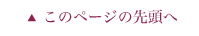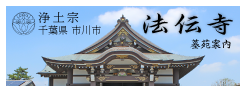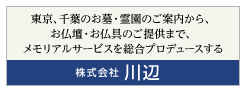圓勝院墓苑をご案内する、東京都江戸川区の石材店、株式会社川辺からのご案内
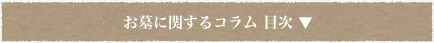
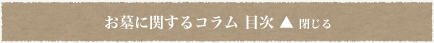
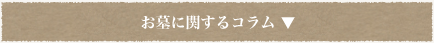
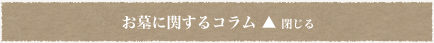
お墓参りの仕方
お墓参りには特別な作法はありません。先ずはご先祖様に感謝して手をあわせましょう。
近況の報告や日頃の感謝の気持ちを伝え、心を込めてお祈りするのが良いでしょう。
(1)墓地のお掃除
お墓の周囲をきれいに掃き、ゴミがあったらを拾いましょう。墓石が汚れたりコケの生えている場合は、水をかけながらたわしで洗ってきれいにします。線香台、水鉢、花立もブラシなどで丁寧に洗います。
(2)お供え・焼香
墓石に打ち水をして、花立に花を添えます。水鉢の水を入れ替え、故人の好物だった菓子・果物などをお供えします。そしてろうそくとお線香を手向けます。
(3)墓石に水をかけ合掌
合掌礼拝の前に水桶からひしゃくで水をすくって墓石にかけます。水はたっぷり墓石の上から水をかける方がよいとされています。
水をかけた後は手を合わせてお祈りをします。
その後は、お寺で借りた用具はきちんと戻し、お参りを終えます。
埋葬のかたち「永代供養墓」
永代供養墓は、お墓の承継者がいなくても、管理するお寺が永代にわたり供養するお墓です。
一般的なお墓はそのお墓を承継する人が絶えれば、一定の手続きを経た上で無縁墓として改葬されますが、永代供養墓の場合は弔い上げ(33回忌、50回忌)になるまで責任持って僧侶等に供養され、安置されることになります。
【永代供養墓の主な特徴】
(1)誰かがお墓参りしなくてもお寺が責任を持って永代にわたって供養と管理をしてくれる
(2)一式料金を一度支払えば、その後管理費、お布施(お塔婆代など)寄付金など一切費用はかからりません
(3)宗教宗派が不問の場合がほとんどです
(4)共同墓の場合は墓石代がかからないため割安になるなど、一般のお墓と比べて料金が安いことが多くなっています
真言宗豊山派 圓勝院 墓苑案内 - 川辺 Copyright(c) 2013.Enshoin Boen Annai .All Rights Reserved.